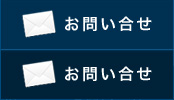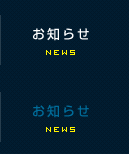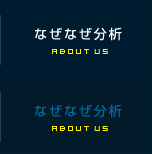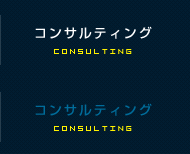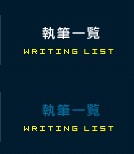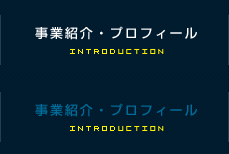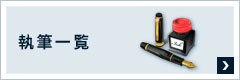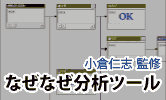小倉仁志プロフィール
 おぐら ひとし
おぐら ひとし
小倉 仁志
・有限会社マネジメントダイナミクス 社長
・一般社団法人 神奈川県中小企業診断協会 元会長
経歴
| 1962年 | 静岡県富士市生まれ、横浜育ち(小学校以降、一部札幌) |
| 1985年 | 東京工業大学(現 東京科学大学) 工学部 化学工学科卒 |
| デュポン・ジャパン(現 デュポン)入社
合成樹脂事業本部エンジニアリング・プラスチック事業部にて主に技術営業に携わり、ポリアセタール樹脂やナイロン樹脂、ポリエステル樹脂に関する技術のカスタマーサポート(設計、加工、検査)に従事。
後半は培った技術を生かした営業を展開。 【対象業種】
|
|
| 1992年 | 社団法人日本プラントメンテナンス協会に転職
国内外の製造業や営業所において、人を中心とした体質改善を図りながら、災害ゼロ、不良ゼロ、故障ゼロを目指すTPM(トータル・プロダクティブ・メンテナンスまたはトータル・プロダクティブ・マネジメント)の指導に従事。開発から営業に至るまでの仕組みや体質改善を手がける 【支援実績】 |
| 1993年 | 中小企業診断士取得 |
| 1997年 | 1993年より「なぜなぜ分析」のルール化、体系化に取り組み、国内初の「なぜなぜ分析」に関する書籍を同協会より発刊。
「なぜなぜ分析徹底活用術」(1997年) 「なぜなぜ分析実践指南」(2000年) 「なぜなぜ分析徹底攻略ドリル」(2002年) |
| 2002年 | 「なぜなぜ分析10則」をまとめ、書籍や通信教育のテキスト、セミナーなどにて「なぜなぜ分析」を啓蒙。
【TPM指導したおもな業種】
【なぜなぜ分析を指導した企業】
|
| 2005年 | 独立し有限会社マネジメント・ダイナミクスを設立。
製造現場や営業所などにおける基盤強化支援や、「なぜなぜ分析10則」および改善に関する指導・社内教育を展開。それぞれの企業に合ったアプローチをモットーに指導を展開。現在まで、「なぜなぜ分析」に関するセミナー・社内教育(年100数十件)を実施。
実際に発生したトラブルの原因追究を一緒に実施していきながら、内部の問題点を洗い出し、改善を一緒に実施していくやり方を得意とし、さらに思考の変革を核に企業の体質改善を支援する。
「なぜなぜ分析」の研修では、製造業全般(自動車部品、電気・電子、石油化学、セメント、医薬品、医療器具、食品、家庭用品、印刷など)、船舶修理、ガス、電力などで実績がある。
お客様からのご意見、ご要望を、漏れなく聞き取り、その情報を企業活動に活かすための取り組みについて、某企業のお客様相談室のメンバーとともに現在も取り組んでいる。 |
| 2006年 | (社)中小企業診断協会 神奈川県支部 理事 を拝命 |
| 2009年 | 2002年度の「なぜなぜ分析10則」をさらに改良し、特にヒューマンエラーについての原因追究のやり方を充実させた「なぜなぜ分析10則-真の論理力を鍛える-」を日科技連より発刊 |
| 2010年 | 日経BP、日経情報ストラテジーにて連載コラムが単行本化
「なぜなぜ分析 実践編」が日経BPより発刊 |
| 2012年 | 一般社団法人神奈川県中小企業診断協会 会長 を拝命
一般社団法人中小企業診断協会(本部) 理事 を拝命
日経BP、日経情報ストラテジーにて連載コラムが単行本化 管理者向け「なぜなぜ分析 管理編」が日経BPより発刊 |
| 2013年 | 「なぜなぜ分析」初の文庫本、日経新聞出版社(日経ビジネス文庫)より発刊
「問題解決力がみるみる身に付く 実践 なぜなぜ分析」 |
| 2014年 | 日経BP、日経情報ストラテジーにて連載コラムが単行本化
「クイズで学ぶ なぜなぜ分析超入門」が日経BPより発刊 |
| 2015年 | 「なぜなぜ分析」文庫本、第2弾、日経新聞出版社(日経ビジネス文庫)より発刊
「現場力がみるみる上がる 実践 なぜなぜ分析」 |
| 2016年 | なぜなぜ分析に欠かせない業務改善についてまとめた書籍を日本実業出版社より発刊
「現場で使える問題解決・業務改善の基本」
一般社団法人神奈川県中小企業診断協会 会長を、2期目の任期満了にて退任 同時に、一般社団法人中小企業診断協会(本部)理事を退任
一般社団法人神奈川県中小企業診断協会 監事も務める |
| 2023年 | 観察力と表現力は表裏一体。
新たな試みにチャレンジした書籍が、日経BP,日本経済新聞出版より発刊。 「『秒』で伝える 『観察力』×『表現力』を鍛える100のレッスン」 |
| 2025年 | なぜなぜ分析の集大成となる書籍を、日科技連出版から発刊。
「現場・職場・組織を変える なぜなぜ分析活用術 全員で取り組む原因追究の強化書」 |
2020年度の言葉

| 失敗の原因追究に管理職も入って、自ら改善策を出す |
皆さんは、失敗を当事者だけに関わる問題で済ましてはいないだろうか。
失敗に至ったいきさつをはっきりさせて、なぜ失敗が発生したのか掘り下げていくと、ほとんどの失敗は当事者の関わる問題だけでなく、業務全体あるいは管理職の関わる問題もあることに気づく。
失敗というのは、会社や職場の脆弱な部分が、たまたま形になって表れてきたに過ぎない。
優れた管理職ほど、部下の失敗を見て、自らが関わる問題にも気づき、すみやかに改めていく。
管理職が自ら関わる問題に気づかず、失敗した当事者や関係者を攻めるのは論外である。
次回失敗しないためにはどうしたらよいか、管理職と当事者が一体になって、全員分の改善策を出すつもりで原因追究を進めることが大切だ。
コロナ禍により新たな取り組みが始まった職場や企業も少なくない。新たな取り組みの中での失敗であればなおさら、失敗の当事者と管理職が一緒に考えていく。
いち早く業務全体を変えていけるかどうかが、企業の生き残りの成否のカギを握ることはいうまでもない。
2020年8月12日 小倉 仁志